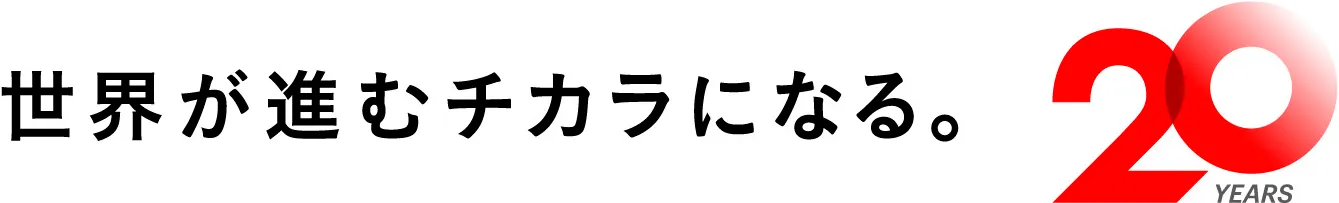MUFG Innovation Partners (MUIP) の代表取締役社長である鈴木伸武が、先月開催された世界最大級のフィンテックイベント「Global Fintech Fest 2025」に登壇した。
「国境を越え、資本を越えて:グローバルなフィンテック投資のプレイブックを構築する」と題されたセッションには、TVS Capital Funds 会長の Gopal Srinivasan 氏、Z47 マネージングディレクターの Vikram Vaidyanathan 氏、Yes Bank カントリーヘッドの Ajay Rajan 氏も参加。セッションで最も時間が割かれたのは、グローバルフィンテックがインドで成功と失敗を分ける要因、特にローカライゼーションの重要性についての議論だった。
Facebook、Instagram、WhatsApp はインドでもグローバルブランドのまま成功している。
しかし金融サービスとフィンテックでは様相が異なる。消費者向けモバイル決済は外資系企業が支配しているものの、それらは深くローカライズされたインド企業として機能している。というのも、金融サービスは製品、テクノロジー、人材、規制のすべてにおいて極めてローカルなビジネスであるからだ。
さらにもうひとつ、インドの銀行は世界的に見ても質が高く、フィンテック採用が始まった時点で顧客満足度も高かったという背景がある。
そのため、この市場で競争するために必要な人材の質は、他のどこよりも高い水準が求められる。Yes BankのAjay 氏は、成功した企業の共通点として「外資企業だから成功したのではなく、豊富な外国の資本を使いながら現地に最適化したサービスを提供するインド企業になったから成功した」と指摘する。
彼らはインドの消費者に合わせて適応し、インドのために、インドで構築したのだ。
多くの多国籍企業はグローバル製品を作り、それを様々な国で展開しようとする。いくつかの地域では機能するかもしれないが、インドでは機能しない。インドのためには、インドで、インドのために作らなければならない。
こうした背景を踏まえ、鈴木はインド・フィンテックにおけるローカライゼーションの重要性を、日本市場での具体例を通じて補強した。
PayPay が示すパートナーシップの力

Paytm は、SoftBank Vision Fund から投資を受けただけでなく、日本市場では SoftBank とパートナーシップを組んで QR コード決済サービス PayPay を立ち上げました。現在、PayPay は日本のモバイル決済市場で最大のシェアを持っています。これはインドのフィンテック企業と日本企業のパートナーシップによる大きな成功例です (鈴木)。
この事例が示すのは、テクノロジーやビジネスモデルの優位性だけでは不十分で、現地の事業会社や金融機関との戦略的提携が市場浸透の鍵になるという現実だ。鈴木はインドのスタートアップが国際展開する際の戦略についても明確な見解を示す。
インドのスタートアップには、豊富なエンジニアリング人材という点で大きな優位性があります。柔軟な規制環境やUPI等の公共インフラも活用できます。しかし、何より重要なのは、各市場における顧客行動を理解し、インドとは異なる規制に対応しながら、現地でのビジネスを構築することです。この取り組みを通じて、良い現地ビジネスを作ることができます。そして、パートナーシップが重要です。各市場で良いパートナーを見つける必要があります (鈴木)。
一方、TVS Capital の Gopal 氏は、グローバル企業がインドで成功するための「4つのL」フレームワークを提示した。
Large market(大きな市場)、Language(言語)、Learn to leverage(活用を学ぶ)、Localization(ローカライゼーション)がそれで、特に強調されたのが「規制の言語」を理解することの重要性だった。
RBI のルールが違って見えるのは、日銀や他国のルールに慣れているからで、規制もまたインドの言語なのだ。成功例として挙げられたのは、Matrix、Peak 15、Norwest といった外国資本のファンドで、彼らは完全にローカライズし、こうした言語を理解しているという。
もうひとつ、パートナーシップと並んで重要なのが、規制への対応だ。鈴木は外国投資家の立場から、インド市場特有の課題を率直に語る。
外国投資家として、インドは規制面で複雑さがあるのは事実です。RBI や SEBI など複数の規制機関が存在しますが、これは米国のような連邦制の国でも同じです。ただ、インドの場合、急速な成長に伴って規制も頻繁に変化しています。だからこそ、常に最新の規制動向をキャッチアップする必要があります (鈴木)。
鈴木は投資先企業に対し、高い専門性を持つ法律事務所や業界団体とパートナーシップを結ぶことを推奨している。
Gopal 氏は、規制の抜け穴を利用して利益を得ようとする企業は思わぬトラブルを招く恐れがあると警告。一方で、インドの規制当局は17年間見てきた中で最も聞いて議論する姿勢を持っており、忍耐強くオープンマインドだと評価した。パネリストたちは、規制やコンプライアンス対応にかかるコストをビジネスモデルに最初から織り込むこと、そして規制の精神に従うことの重要性を強調した。
グローバル展開の実践——アフリカから日本まで

ローカライゼーションの原則は、インド企業のグローバル展開においても同様に適用される。鈴木は、インドの DPI(デジタル公共インフラ)を海外展開する際の戦略について明確な見解を示した。
DPI やインフラを輸出するなら、アフリカのような新興国を狙うべきです。ブラジルのような国はすでに洗練された金融インフラを持っていますが、アフリカにはまだそうした基盤が不足しています。だからこそ、市場を構築できるチャンスがある (鈴木)。
成熟した市場では既存のインフラとの競合が避けられないが、インフラが不足する市場では、インドの実績あるソリューションが大きな価値を提供できる。アフリカは人口が14億から15億人とインドに匹敵する規模で、金融包摂の課題が深刻だ。インド政府もアフリカとの関係強化に注力しており、インド系ディアスポラ(海外在住インド人コミュニティ)が多い UAE も有望な市場として挙げられた。
一方、日本のような成熟市場への展開には、より高度なローカライゼーション戦略が求められる。聴衆からの質問に答える形で、鈴木は日本の決済システムの独自性と、そこから得られる教訓を語った。
日本の決済システムは独自の進化を遂げています。たとえインド企業がより良いソリューションを持っていたとしても、日本市場に適応する必要があります。技術プラットフォームのコア部分と、現地適応のためのアダプター部分を区別することが重要です。
インド企業は日本の決済システムのためのコア技術プラットフォームをすでに持っているかもしれません。しかし、その上に、日本の金融機関やシステムに適応するための良いアダプターが必要なのです。品質と応用を分けて考える必要があります。そうした意味で、インドと日本の両方の金融システムを理解する良いパートナーを持つことが必要です (鈴木)。
コア技術は維持しながらも、現地の文脈に合わせた適応層を設けることで、真のローカライゼーションが実現する。鈴木が求めるパートナーとは、単なる翻訳者やコンサルタントではなく、両国の金融システムの本質を理解し、架け橋となれる存在だ。このローカライゼーションの原則は、AI 時代においても変わらない。
鈴木はインドが多様な金融データを持つことで AI にとって独自の優位性があると指摘。パネリストたちは、インド人が他国よりも音声を使うことを好む傾向や、インドのフィンテック企業が1日あたり100万から200万件の通話を処理している事実を挙げ、音声エージェント技術においてインドが最前線に立つ可能性を示した。
各市場のユーザー行動、データの特性、現地のニーズを深く理解し、それに適応する能力こそが競争優位性の源泉となる。ローカライゼーションとは、単なる言語翻訳や UI の調整ではない。市場の文脈、規制の精神、ビジネス慣行、人材の質、パートナーシップのすべてを含む包括的な取り組みだ。
鈴木が繰り返し強調したのは、パートナーシップの決定的な重要性だった。PayPay の成功、コア技術とローカル適応を分離する戦略、両国の金融システムを理解するパートナーの必要性。これらは単なる事業拡大ではなく、相互学習と長期的な価値創造を目指す MUFG の姿勢を反映している。日本とインドという異なる市場で培われた知見を相互に活かし、両国のフィンテック産業の発展に貢献する。その架け橋としての MUFG の役割が、このセッションを通じて鮮明になった。