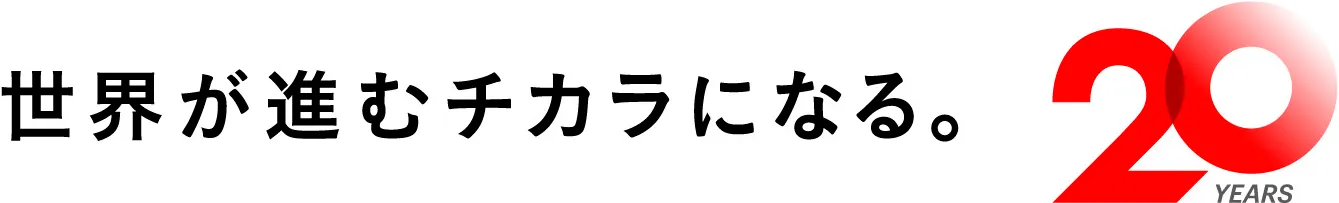三菱UFJフィナンシャルグループが「さぁ、世界を驚かせに行こう!」というスタートアップ領域のタグラインを新たに掲げるなど、大企業とスタートアップの共創による日本の経済・社会変革が加速している。SusHi Tech Tokyo 2025のプレゼンテーションで、MUFG代表取締役社長兼CEO亀澤宏規氏はオープンイノベーションの3つの形態を提唱。
続いて三菱UFJ銀行事業共創投資部長の亀元護氏が具体的な実践事例を紹介した。保守的というイメージを覆し変革する日本企業の姿と、スタートアップとの共創を通じた社会課題解決への道筋が示された。
亀澤宏規氏が語る「3つのC」によるオープンイノベーション
「大手日本企業」という言葉から多くの人は「保守的」「動きが遅い」というイメージを抱くかもしれないが、三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG)代表取締役社長兼CEOの亀澤宏規氏によれば、現実には大きな変革が起きている。
今日の日本は、激しく進化する世界の要求に対応しながら、急速に前進する道を歩んでいます。大手日本企業は、最先端技術と大胆なビジネスモデルを持つスタートアップとの協業を通じて成長を促進しています(亀澤氏)。
日本は成長の時代に入っており、経済的・社会的安定性という強みを持つ。また、モビリティ、材料、量子コンピューティング、環境技術など多くの分野で技術的優位性があり、これらが新たなイノベーションの土壌となっている。政府の積極的な施策もあり、東京は2024年のグローバルスタートアップエコシステムランキングで初めて世界トップ10に入った。
こうした背景のもと、亀澤氏はオープンイノベーションを促進する「3つのC」を提案した。
オープンイノベーションを促進する3つの重要な形態があります。1つ目は『協働(Collaboration)』で、大企業がスタートアップと連携して新しい価値を創造すること。2つ目は『事業共創(Co-creation)』で、複数の大企業とスタートアップが協力して新しい産業や新しいバリューチェーンを創出すること。そして3つ目は『支援(Contribution)』で、スタートアップの成長を加速するためのサポートを行うことです(亀澤氏)。

この枠組みは単なる概念ではなく、具体的な成功事例によって裏付けられている。「協働」の例として、亀澤氏は MUFG が投資した AI 企業 Sakana AI 社を挙げた。設立からわずか2年の企業だが、グローバルレベルのトップクラスの AI 人材を持ち、Nature 誌などに革新的な研究結果を発表。MUFG の膨大なデータリソースと当社の技術力を組み合わせることで、革新的な AI アプリケーションの可能性を開拓している。
「事業共創」の例としては、和歌山県にある日本初の民間ロケット発射場から小型ロケットを打ち上げる スペースワン社 がある。MUFG は、当社への出資に加え、ロケット製造の国産化や品質向上などの課題に対処するために地元企業とのビジネスミーティングを開催し、宇宙ビジネスの社会的価値を高めるエコシステム構築を支援している。
「支援」については、昨年東京証券取引所グロース市場に上場したタイミー社の事例を紹介。MUFG はデットファイナンスの提供から始まり、大規模な資金調達サポート、IPO 支援と段階的に関係を発展させた。亀澤氏は IPO 後も地域雇用創出プログラムなど多角的な支援を継続していることを強調した。
プレゼンテーションの締めくくりとして、亀澤氏は MUFG のスタートアップ領域の新たなタグライン「さぁ、世界を驚かせに行こう!」を発表。これにはスタートアップとともに日本発のイノベーションをグローバルに展開していく意思が込められている。
「このレベルの驚きを生み出すことは MUFG 単独では達成できません。スタートアップを取り巻くステークホルダーの皆さまとの協力が必要不可欠です。このメッセージは SusHi Tech Tokyo の理念に完全に合致していると思います」(亀澤氏)。
日本のオープンイノベーションは今や理念や構想の段階から、具体的な実践と成果の段階へと確実に進んでいる。大企業の本気度とスタートアップ側の活力が相まって、新たなイノベーションの潮流が生まれつつあるのだ。
亀元護氏が示す実践的アプローチと課題解決

亀澤氏に続いて登壇する三菱UFJ銀行事業共創投資部長の亀元氏は、オープンイノベーションの実践的アプローチと具体的な課題解決策について語った。
オープンイノベーションの促進が様々な社会問題の解決と日本経済の加速において重要です。多様なステークホルダーが新しい製品や戦略を積極的に生み出せる社会を育むことが必要です(亀元氏)。
亀元氏によれば、歴史的に多くの日本企業は自社内で技術を開発することで成長してきたが、現在の複雑な社会課題に対応するには、異なる強みを持つ多様なプレーヤーの協力が不可欠だという。
コラボレーションは大企業とスタートアップの間だけで行われるべきではありません。大学や政府機関など、より幅広いプレーヤーに開かれています(亀元氏)。
オープンイノベーション推進の課題としては、文化的・実務的な障壁がある。過去の成功体験が新しい試みを阻むことや、意思決定プロセスのスピードが課題となる。また、社会変革は少数の革新的な取り組みだけでは持続できず、産業界の大多数の考え方と行動を変える必要がある。
こうした認識のもと、MUFG は日本経済に意味のある変化をもたらす新しいプラットフォームを開発している。亀元氏はその例として、産業プラント分野での AI・ロボティクス活用を紹介した。
石油・ガス、化学企業などの大規模産業プラントを運営する企業では、設備が非常に複雑で、技術に対する高いレベルの品質要求があります。また、それらのほとんどは、設備の老朽化などの共通の課題に直面しています(亀元氏)。

MUFG は建設と検査の両分野で AI とロボティクスを活用するスタートアップと協力。このスタートアップはハードウェアからデータ解析、アプリケーション開発まで一貫した強みを持ち、MUFG はその潜在的クライアントを繋ぐ支援をしている。
もう一つの例として、ベンチャークライアントモデルを活用したオープンイノベーションの取り組みがある。このモデルでは、企業が自社の戦略的利益を明確にした上で、必要となるスタートアップの製品やサービスを、まずは最小単位で購入することを促す手法だ。
オープンイノベーションには2つの大きな障壁があります。一つは製品の品質と適合性に関する議論であり、もう一つは意思決定プロセスのスピードに関する問題です(亀元氏)。
MUFG はベンチャークライアントモデルがこの課題を乗り越える手法だと考え、実際のビジネスへ適用していくためにはこの方法を理解するだけではなく、様々な機能や企業を巻き込んだエコシステムを作り出すことを実践している。JR東日本とのパートナーシップ協定や、政府系機関との協力も進めており、この方法を日本全体に広げる活動を進めているという。
さらに注目すべきは、MUFG が海外のスタートアップとの協力にも積極的に取り組んでいる点だ。国境を越えたオープンイノベーションの構築により、より幅広い社会課題解決と経済成長を実現する可能性が広がっている。
亀元氏は最後に、オープンイノベーションを共に推進するための幅広い関係機関との協力の重要性を強調した。
大企業とスタートアップの二者間の関係にとどまらず、大学や政府機関、地域社会も含めた幅広いエコシステムの構築が、今後の鍵となるだろう。こうした多様なステークホルダーの参画によって、日本発のオープンイノベーションは新たな段階へと進化していく。