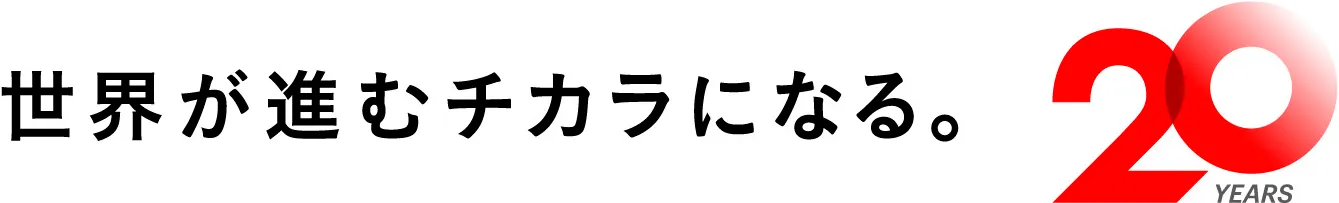生成 AI を活用した大企業とスタートアップの協業はどのような結果を生むのか。三菱UFJ信託銀行とカサナレの事例はその好例といってよいプロジェクトだろう。
2024年4月、三菱UFJ信託銀行の市場取引業務での導入を皮切りに、カサナレの生成AIプロダクト「Kasanare」は着実に実績を積み重ねてきた。最初の導入では社内問い合わせ対応業務を50%削減し、90%以上の高い正答率を達成。その後、二例目として他の業務での導入も実現し、三菱UFJ信託銀行内での活用が広がっている。
こうした成果は、単なる業務効率化にとどまらず、従来は個人の経験や勘に依存していた暗黙知を、AIを通じて形式知として蓄積・共有するナレッジマネジメントの取り組みとしても重要な役割を果たしている。カサナレは現場の知見を可視化し、組織全体の知識資産として活用することで、持続的な業務改善と人材育成にも寄与してきた。
そして今回、三例目の取り組みとしてリテール業務におけるカサナレのAIアシスタント導入が決定された。これまでの実績に加えて、カサナレの顧客に寄り添う提案力や信託銀行の専門的な業務への理解、スピードやシステム、導入後支援に関する柔軟な対応力が総合的に評価された結果だ。
リテール業務への導入成果は驚くべきものだった。問合せ対応部署および、とある支店の社員での3か月の実証実験を経て全社での導入が決定し、年間最大6万5,000時間の効率化が見込まれている。
数字だけ見れば華々しい成功事例に見える。しかし、そこに至るまでの道のりは決して平坦ではなく、カサナレと三菱UFJ信託銀行の信頼関係があったからこそ実現したものだ。事業開発担当として、その舞台裏を記録しておきたい。
実現不可能への挑戦

2024年8月、三菱UFJ信託銀行の事務管理部で生成 AI エージェント「Kasanare」の取り組みが始まった。このプロジェクトが目指したのは、リテール業務に携わる社員が直面する、業務上必要な情報をマニュアルなどの膨大なドキュメントから検索することの負荷軽減だ。
三菱UFJ信託銀行では元々生成 AI を活用した社内業務の効率化に向けて複数のユースケースでの検証を開始していたが、その中でも成功した場合の効果が最も大きいユースケースとして、事務管理部でのプロジェクトが始まった。本部と全国の支店に在籍する約2000人に関わる一大プロジェクトだ。
ここでカサナレが挑戦したのが、膨大な社内業務マニュアルや FAQ文書から、三菱UFJ信託銀行専用の独自アルゴリズムを開発することだった。膨大な文書から適切な情報を抽出し、高精度を維持しながら実用レベルの回答を生成する——。「現在の技術では実現困難」と判断されてもおかしくないレベルへの挑戦だった。
——企画から開発にあたっての最大の壁を教えてください
ユーザー部として生成AIを実務で使う上で、まずは回答精度が突き詰めるべきポイントでした。そこはカサナレさんに我々の要求を満たすプロダクトを提供していただくことができましたし、導入後も改善し続ける仕組みになっています。次に、ユーザーにどうやって使ってもらうかが課題でした。絶対的に正しい回答を求める人が一定数いるのですが、必ずしもそうではないということを分かった上で使いこなす必要があります。正しい質問をすると回答がきちんと返ってくる、その体験をどれだけ積んでもらえるかという点に苦労しましたし、それは今後も課題であり続けると思います(河野氏/三菱UFJ信託銀行)。
最初の時点の要求がそもそも今の当たり前では実現できないところから始まりました。精度や納期、システムの要件等、どこをとってもそれ難しいんじゃないのという状態から入りました。要求もハードな中で、できるであろうという自信はあったものの、色々なチャレンジングな目標を乗り越えながら進行する必要がありました。AIプロジェクトでは、データを読み込ませてみなければAIの挙動が分からないという「後から課題が判明する」ような構造的な難しさもあるのですが、まさに壁の連続でした(安田氏/カサナレ)。
突破口となったのは、現場の人々との密接な連携だった。技術的にギリギリの状況において、現場からのフィードバックや協力を得ながら、段階的にプロダクトを完成させていく手法を取った。関係者全員が「一緒にこれを成功させよう」という気持ちを共有できたことが、プロジェクト成功の鍵となった。
ワンチームでの奇跡的な協働成果

約1年の開発期間を経て実現した成果は、当初の期待を大きく上回るものだった。単なる業務効率化にとどまらず、ユーザー満足度においても極めて高い評価を得た。一般的に SaaS系の生成AIプロダクトの導入では一定の不満や改善要望が出るものだが、今回は全く異なる結果となった。
さらに特徴的なのは、プロジェクトの進行過程で生まれた協働体制だった。従来の大企業とスタートアップの関係は、発注者と受注者という上下関係がどうしても生まれる。
しかし、このプロジェクトでは目指す水準の高さゆえに、むしろ対等なパートナーシップが必要となった。大企業とスタートアップがワンチームとなって成果を上げた好例と言ってよいプロジェクトだろう。
——最終的にどういった成果が上がっていて、カサナレさんをパートナーとして選んでよかったところは何でしょうか
試行店での実績を踏まえて効果を数値で示すと、最大で年間6万5,000時間の業務効率化が図れる見込みで、かなりインパクトのある数字となっています。
定性的な効果は、ユーザーが情報を探す手間から解放されたという点が挙げられます。ユーザーにアンケートを行った結果、全員が「このAIアシスタントが業務に役立つ」「これからも使い続けたい」と回答しています。みんなが使い続けたいと思うツールはなかなか珍しいんじゃないでしょうか。カサナレさんのことは、単にパートナーさんという感覚ではなく一緒にプロジェクトを成功させるためのチームのメンバーだと思っています(河野氏)。
カサナレさんと取り組んでよかった点は、カサナレさんが常に信託の立場になった提案をしてくださり、現場に寄り添って本プロジェクトを進めてくれたことです。また本プロジェクトでは、AIを導入して終わりではなく、その後もユーザーからのフィードバックをもとに改善し続ける仕組みを構築することができました。信託銀行の専門性の高い多様な業務に関する暗黙知を形式知化していくことは急務であり、カサナレさんと構築した仕組みが今後大きな役割を果たすと考えています(海老名氏)。
——カサナレさんとして、金融機関ならではの難しさなどはあったのでしょうか
AIが回答した内容の説明可能性(回答の妥当性)やハルシネーション対策など、厳しい条件をクリアすることはAIを使う上での最低限の条件だと思っています。金融機関だから特別ということではなく、AIを使っていく上での必要な条件を満たすことが、まだまだ業界的にチャレンジングな目標でもあり、かつ私達に求められていることだと感じています(安田氏)。
AI 活用の本質

このプロジェクトから見えてきたのは、AI 活用における本質的な考え方だ。多くの企業において「AI を導入したい」という技術先行の発想でプロジェクトを進めてしまうことがある。
当然ながら成功の鍵は全く逆のアプローチにある。
まず現場の困りごとを徹底的に理解し、その解決手段として AI を位置づける——。シンプルに聞こえるが、実際には現場と本社の協力が必要な、決して簡単ではないアプローチだ。
また、AI アシスタントの実用化において重要なのは、単純な情報提供を超えた「プロフェッショナルな判断力」の実装だった。正しい情報であっても、それを伝えるべきタイミングや相手、表現方法を理解できなければ、実際のビジネス現場では使い物にならない。カサナレが目指すのは、こうした細やかな配慮ができる AI アシスタントの構築だ。
——大企業で AI 活用を考えている人たちへのアドバイスや重要なポイントなどご意見をお伺いしたいと思います
AIを活用したいという思いだけでは、うまくいかないのではないかと思います。まず、目の前の業務や現場で困っている課題を解決したいという気持ちがあり、そのソリューションの1つとしてAIがあるイメージです。
AIを活用したいと思っている会社こそ、目の前の現場の業務を知って、困っていることにしっかり目を向けることが重要です。そして、カサナレさんのようなAIの技術を持っている方に相談しながら取り組んでいくことが一番の成功の近道だと考えます(河野氏)。
まさにその通りで、業務課題をしっかり把握することが重要です。一方で、現場だけでスタートアップとの協業やAI導入の判断を進めるのは、難しい場面もあります。そうした場合には、技術的な知見を持つ部署、例えば私たちデジタル戦略部のような立場が、伴走しながら支援することで、プロジェクトの不確実性を減らすことができます。私たちも、現場の課題に寄り添いながら、単なる個別対応にとどまらず、中長期的な視点や全社最適の観点を持って取り組むことを意識しています。現場が安心してチャレンジできるよう、技術面だけでなく、予算や社内調整も含めた支援体制を整えることが、結果的にAI活用の成功につながると感じています(海老名氏)。
——このプロジェクトでの学びを次にどのように生かしていきますか
今後は信託銀行内の様々な業務において、カサナレが作ったAIアシスタントがプロフェッショナルな仕事を代替していくことができると思います。リスクテイクという話だと、ビジネスにおいては、正しいけれど言ってはいけない、知っているけれど出してはいけない情報があります。生成AIの導入効果は「正答率」で語られることも多いですが、必ずしも正解を答えることが正しいとは限らず、相手の求める情報を、公開可能な情報範囲の中で伝えなければならないケースも沢山あります。そのような高度な判断ができるAIを他の部署にも展開し、さらなる業務効率化や暗黙知の形式化に貢献していけたらと思っています(安田氏)。
2024年8月の取り組み開始から現在まで、プロジェクトは順調に成果を上げ続けている。このプロジェクトが示した、現場の課題に真摯に向き合い、社内外のステークホルダーの力を結集して解決するアプローチは、日本の生成 AI 活用において一つのベンチマークになることを確信している。