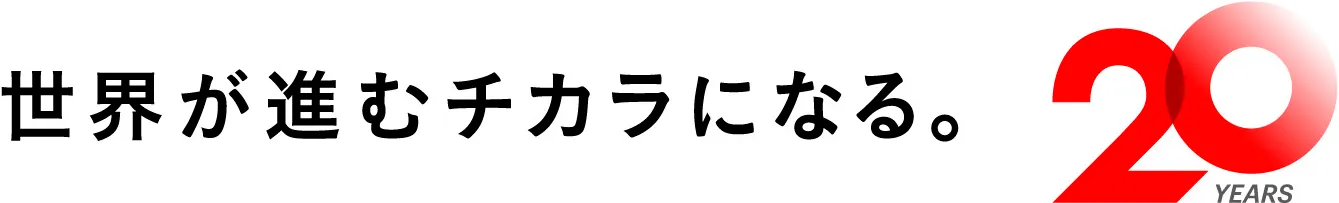今年7月に開催されたIVS のセッション「戦略の解像度が未来を変える - 10→100フェーズの勝敗を分ける意思決定とは」でモデレーターを務め、八木智昭氏(タイミー取締役CFO)、田中優子氏(クラウドワークス元取締役)、戸田翔太氏(dely取締役CFO)という第一線で活躍する経営者たちと、成長企業が直面する戦略転換について深く議論する機会を得た。
このセッションを通じて改めて実感したのは、日本のスタートアップエコシステムが確実に新たな成熟段階に入っているということだ。投資家として数多くの企業を見てきた立場から、その変化の本質と今後の展望について記しておきたい。
戦略転換の最前線で見えた成長企業の本質

まず印象的だったのは、田中氏が語ったクラウドワークスの戦略転換だ。同社が2020年から2021年にかけて行った「赤字前提からの脱却」は、日本のスタートアップ市場全体の変化を象徴している。
トップライン成長を最優先した継続的な赤字によりキャッシュフローが悪化し、将来の投資機会を失うリスクに直面していた同社は、根本的な意思決定を行った。しっかりと利益を出しながら成長させていくという方針転換である。この決断に至るまでには、M&A での失敗経験も大きく影響していた。
田中氏が振り返ったのは、シナジー創出ができなかったM&Aやコーポレート体制の不備による開示遅延といった苦い経験だった。監査法人から飛んだ厳しい指摘のエピソードのあたりはなんとも生々しかった。
その後の組織改革では、売上総利益に対する人件費の目標を大幅に改善する生産性目標を設定し、毎週の全社朝会でバトル形式の発表会を導入。
2チームが生産性向上施策の成果を競い合う仕組みを1年以上継続することで、コスト意識と効率性向上を企業文化として根付かせた。「経営の意思決定を早くし、何かコスト削減できるところはないか、効率を改善できるところはないかという文化が作られた」と田中氏は語った。
八木氏が語ったタイミーの戦略は、プラットフォームビジネスの本質を捉えている。同社のスポットワークは、オンラインではなくオフラインの仕事のため、現地に行く必要がある上に、エリアごとに需要と供給のバランスを維持する必要がある。タイミーが最初に面を広げるという戦略を取った結果、各地にシェアを持っていることが他社にとっての競争優位性となっているのだ。
プラットフォームの規模とクオリティの関係性についての分析も参考になった。後発企業が参入する際、規模がなければ人が集まらない。人が集まらないと需要サイドも仕事を発注もできず、またクオリティも担保しづらくオペレーションが成り立たない。この二つの壁を突破するため、タイミーは一定の閾値を超えることを最優先に、一気に投資を行った。
また、競合企業も巻き込んで市場全体を拡大するという視点も注目すべきだ。自分たちだけでなく、業界全体で新しい市場を育てていくという考え方で、全国でトップシェアを確保している。これは従来の日本企業が苦手としてきた発想だが、グローバル市場で競争するためには必要な戦略思考だ。
戸田氏による dely の M&A 戦略も興味深い。同社は2018年、ヤフー(現LINEヤフー)の連結子会社となり、その後上場を果たすというスイングバイIPOをした経験を持つ。この買収される側の経験を活かし、現在は積極的に M&A を展開している。
同社が重視する M&A の評価軸は4つある。ブランドや顧客基盤の活用可能性、競合に対する優位性の構築、エンタープライズ向けビジネスでの差別化、そしてテクノロジーでの勝負だ。ただし、テクノロジーについては「GAFAと真っ向から勝負はしない」と率直に語り、経験から学んだ結果が共有された。
M&Aも含めた事業ポートフォリオ拡大で意識している点も明確だった。シナジーありの場合はそれを織り込んだ数字で評価し、シナジーなしの場合は対象会社のスタンドアロンのみのバリュエーションで評価する。そしてRule of 50の持続、つまり売上成長率30%、営業利益率20%以上を設定しており、株式市場での投資対象として選ばれ続けることを意識している。
転換点に立つ日本のスタートアップエコシステム

これらの議論を通じて見えてくるのは、日本のスタートアップ市場が確実に転換点を迎えているという事実だ。投資家として数多くの企業を見てきた経験から言えば、この数年で市場の質的な変化を強く感じている。
海外投資家の関心も高まっている。この数年で世界トップクラスの VC が日本のスタートアップに注目し始めており、実際に投資をしている。また外国人研究者が日本人と共に日本で起業し、短期間でユニコーンになるSakana AIのような事例も生まれている。
今回のセッションを通して、成長フェーズに応じた戦略の最適化の重要性が語られた。企業がどの成長段階にあるかによって、優先すべき課題と戦略は大きく変わる。0から1の段階では求められないが、10から100の段階では戦略の解像度が勝敗を分ける。この認識の転換ができないとどこかで成長が行き詰まってしまうが、それを乗り越えられると次なる成長フェーズが待っている。
日本のスタートアップ市場はまだグローバル市場における存在感は小さいが、その伸びしろは計り知れない。投資環境、人材、そしてチャレンジする機会が揃い、またスタートアップが一般的なキャリア選択肢の一つとなりつつあることも、エコシステムの健全な発展を示している。
今回のセッションで語られた各社の戦略事例は、日本のスタートアップが世界に通用する企業に成長するための重要な指針を提供している。利益と成長の両立、プラットフォーム戦略の進化、戦略的な M&A の活用——これらの要素を組み合わせることで、日本のスタートアップは次のステージに進む準備を整えている。
投資家として、この変化の最前線に立ち会えることは大きな喜びだ。日本のスタートアップエコシステムが真の意味で世界と競争できる段階に入りつつあることを、今回のセッションを通じて改めて確信した。
※本セッションは、今年7月に開催されたIVSのオフレコセッションについて、主催であるIVSの許可と関係者の確認の上で、内容を抜粋して掲載をしています。