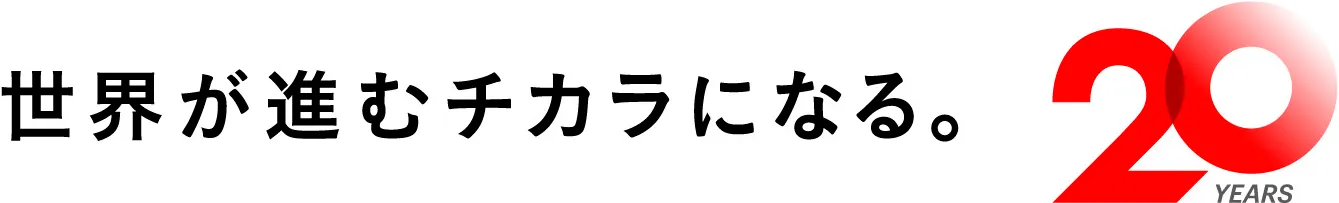ChatGPTリリースから2年半、LLM(大規模言語モデル)技術の進化は企業のDXに「第二のインターネット革命」をもたらしている。特に注目すべきは、大企業が既存SaaSからの脱却を図り、AI活用による業務の内製化を進めている動きだ。
KlarnaがSalesforceやWorkdayの利用停止を発表した話題はインパクトがあったが、なにも話はサードパーティーだけではない。自社の体制もドラスティックに変化している。
例えば米AmazonのジャシーCEOは「AI で従業員が減少する」と明言し、生成 AI による人員削減が顕在化した。米国では Amazon 、Google 、IBM などがホワイトカラーを中心に数万規模の直接レイオフを敢行し、各社が生成AIインフラ投資を拡大している。
何が起こってもおかしくない「LLMパラダイムシフト」の中、スタートアップはどのような戦略を取るべきか——。
6月12日に開催されたBRIDGE×三菱UFJイノベーション・パートナーズ(MUIP)連続勉強会シリーズ第1回では、LayerX、MNTSQ、三菱UFJ銀行の実践者が集結し、「魔王」と呼ばれるビッグテックに対抗する生存戦略を議論した。
大企業の内製化が変える「魔王」時代の到来

生成AIに触れないことがない時代になっていますが、1年半ほど前に出たアメリカのレポートで、AIが雇用にどのような影響を及ぼすかという興味深い調査結果が出ていました(佐野)。
三菱UFJイノベーション・パートナーズ(MUIP)のChief Investment Officerの佐野尚志は、勉強会の冒頭でアメリカの雇用影響予測レポートを引用し、生成AIが知識労働者に与えるインパクトの大きさを強調した。
そのレポートによると、高年収職種ほど生成AIによる影響を受けやすく、リーガル、コンピュータサイエンス、数学、エンジニアリング、金融アナリスト、ビジネスオペレーションといった専門職が、雇用の脆弱性の高い職種として挙げられている。
特に興味深いのは、影響を受ける職種を多く抱える企業の上位30社を見ると、金融機関が11社、情報通信・テック系企業が多数を占めていることだ。
かつてのロボットオートメーションで製造業が効率化された時代から、生成AIは知識労働者により大きなインパクトをもたらしています。これは皆さんにも納得感があるのではないでしょうか(佐野)。
2024年から2025年にかけて、AI技術はさらに進化を遂げている。「さらに昨年から今年にかけて、エージェンティックAIの時代になってきている」と佐野氏が指摘するように、単なる生成AIから、より自律的に業務を遂行するAIエージェントへと発展している。
この変化は、従来の企業とソフトウェアの関係を根本的に変えつつある。
これまでIT予算で導入されたソフトウェアに対して、人々が業務を合わせていました。しかし今後は、ソフトウェアが業務に合わせる時代になります(佐野)。
つまり、「業務をソフトウェアに合わせる」時代から「ソフトウェアが業務に合わせる」時代への転換が起きているのだ。
この変化は、特に日本の企業にとって重要な意味を持つ。少子高齢化が進む日本では、人を雇うのか、AIを雇うのかという選択を迫られる時代の入り口に立っているのだ。
こうした流れを象徴するのが、海外大企業の動きだ。スウェーデンのフィンテック企業Klarnaは、SalesforceやWorkdayといった主要SaaS製品の利用を停止し、独自のAIプラットフォームを構築する方針を発表した。同社は約1,200のSaaS契約を解約し、AIを活用した内製システムへの移行を進めている。
また、小売大手Walmartは社内AIプラットフォーム「My Assistant」を7.5万席に展開し、ドラフト作成や要約作業の高速化を実現している。このような大企業での内製化の動きは、スタートアップにとって市場ニーズの大きな変化を示している。
この状況について、リーガルテック企業MNTSQ代表取締役の板谷隆平氏は「魔王」という印象的な表現で現状を説明した。
大規模言語モデルが出てきて、スタートアップにとって、これはより残酷な時代だと思います。2年前まで、AIというのはスタートアップの独壇場でした(板谷氏)。
しかし状況は一変した。
残念ながら魔王軍が登場しました。特にエンタープライズ領域においては、絶対に倒せない魔王がいます。それはMicrosoft、Google、Salesforce、SAP、Workdayです。彼ら魔王軍が、AIの時代をリードし始めました(板谷氏)。
MicrosoftがCopilotでAI分野をリードし、GoogleがGeminiで対抗し、SalesforceがAgentforceで初のAI機能をSaaSで提供する——。これらビッグテックの参入により、スタートアップにとって競争環境は格段に厳しくなった。
この時代で生きていくのは、よっぽど厳しく、私は残酷な時代だと思っています(板谷氏)。
この「残酷な時代」において、スタートアップはどのような戦略で生き残りを図るべきなのか。その答えを探るために、実際に大企業と協業を進める企業の事例を次章で詳しく見ていこう。
三菱UFJ銀行×LayerX「その会社でしか働けないAI」の構築

「魔王」との戦いにおいて、具体的にどのような戦略が有効なのか。その答えの一つが、三菱UFJ銀行とLayerXの協業事例にある。両社は1年半前から共同でAIを活用した営業ナレッジ共有プロジェクトを進め、大企業特有の課題をAI技術で解決する道筋を示している。
LayerX執行役員AI・LLM事業部長の中村龍矢氏は、同社の戦略をこう説明する。
従来のソフトウェア産業が入り込めなかった、少量多品種に近いような市場を作れるのではないかという着想を得ました。特にエンタープライズの領域は、従来のSaaSではお客さんごとの違いが大きく難しかったのですが、LLMであればそれができるのではないかと考えました(中村氏)。
大企業営業部門が抱える根深い課題

三菱UFJ銀行コーポレートバンキング企画部調査役の木村智彦氏は、AI導入に至った背景をこう振り返る。
私の所属している部門は大企業営業で、かなり数多のオーダーメイドな提案をする部門です。優秀な営業の方は本当に優秀なのですが、結構職人化していて、それがチーム内はもちろん、同じ部門の隣の部の方とはあまり会話することがないなど、属人化が激しかったのが課題でした(木村氏)。
大企業営業では、単純に融資を行うだけでなく、企画部門への提案、ガバナンスやESG、IRといった幅広い領域での専門的な提案が求められる。しかし、こうした高度な業務ノウハウが個人に蓄積され、組織として共有されない状況が続いていた。
当初、同行はTeamsやSharePointといった従来の情報共有ツールでの解決を試みた。しかし結果は芳しくなかった。
全くもって定着しませんでした。共有の手間や、自分が精魂を込めて作った提案書をわざわざ他の営業担当者に渡すのかという問題、また全文検索しないと引っかからないという使い勝手の悪さがありました(木村氏)。
LayerXとの出会いは、まさにこの課題を解決するタイミングで起きた。AIを使ったマスキングや文章の検索性向上、そして何よりスピードと柔軟性が決め手となった。自社開発では時間的にも規模的にも割りに合わないため、外部のSaaSソリューションとして導入に至ったのだ。
Ai Workforce は長文の文書処理に特化したプラットフォームで、営業資料や決算書など何百ページにも及ぶ文書から情報を転記したり、検索しやすくしたりする業務をサポートする。特にAIのハルシネーション(誤った情報生成)を修正するための体験設計に力を入れているのが特徴だ。
基本的にCopilotは、幅広いユースケース向けに作っているので、最大公約数的なUIになっていますが、長文の文書処理に特化し、AIのミスやハルシネーションを直しやすい体験を作り込んでいます(中村氏)。
「うちの会社に特化して活躍するAI」という差別化戦略

では、MicrosoftのCopilotなど汎用的なAIツールとLayerXのソリューションは何が異なるのか。中村氏はこの違いを「ポータブルなスキル」と「ポータブルじゃないスキル」の概念で説明する。
人間の仕事の中には、会社をまたいでも役立つポータブルなスキルと、その会社にいないと役立たないポータブルではないスキルがあります。ポータブルなスキルほど、あまりサポートせずに使えるソリューションが全世界で流行するでしょう(中村氏)。
開発やリサーチといった業務は比較的ポータブルなスキルであり、これらは汎用的なAIツールでも十分対応可能だ。
人間の場合も採用してすぐに役立つわけですから、逆にAIでもそういう使いやすいツールがすぐに生まれると思います(中村氏)。
一方で、世の中の仕事には企業特化のノウハウに基づく業務も存在する。その会社の様々な部署のコンテキストや歴史を横断して学ばなければならない、会社に特化したノウハウに基づく仕事だ。こうした業務は、人間であってもしっかりとしたオンボーディングや教育を受けなければ役立たず、それはAIにとっても基本的には同じことが言える。
LayerXが目指すのは、まさにこの後者の領域だ。
うちの会社に特化して活躍するAIを作りたいというのが、Ai Workforceの世界観です。そういうビジョンが、結果的に個別のユースケースにおける機能差につながっているでしょう(中村氏)。
大企業導入における成功要件

技術力だけでは、大企業市場での成功は保証されない。木村氏が指摘するのは、大企業特有の要件への対応の重要性だ。
まず、セキュリティ要件が最大の障壁となる。
悲しいことに、我々のような大企業は、やはりいろいろなルールや縛りがあります。これは金融機関である私の立場からすると、やはりセキュリティのレベルで、多くのスタートアップが、良いものを持っていると思っても入らないケースが多くあります(木村氏)。
次に、レガシーシステムとの共存問題がある。
うちの会社のホストシステムは私とほぼ同い年のシステムもあります。その頃からのシステムがまだ一部生きているものもあり、今あるものと共存できるのかも重要です(木村氏)。
しかし、これらの要件をクリアすることで得られるメリットは大きい。木村氏によると、技術の尖りに加えて、「我々よりも知識を持っていて、我々が伸ばしたいと思っているところに関して一番とがっていて、かつスピードと柔軟性を保ちながら企業要件を満足させる」企業が選ばれるという。
現在、三菱UFJ銀行とLayerXは単なるナレッジ共有を超えた次のステップを模索している。木村氏によると、現在は蓄積されているものを検索しやすくしているにとどまっているが、より高度なことを目指しており、優秀な営業担当者が作るような提案書を作る世界の実現に向けて協業を進めているという。
この事例が示すのは、汎用的なAIツールではカバーできない企業固有の業務領域にこそ、新たなビジネス機会があるということだ。2〜3ヶ月のチューニング期間で個別最適化されたAIソリューションを提供することで、大企業の複雑な業務要件に応えながら、ビッグテックとの差別化を図る戦略が見えてくる。
「ラスボスのいない領域」で勝負するMNTSQ

LayerX が企業固有の業務にAIを特化させる戦略を取る一方で、まったく異なるアプローチで大企業市場を攻略している企業がある。それがリーガルテック企業 MNTSQ だ。同社も三菱UFJ銀行をはじめとする大手企業に導入されているが、その戦略は「ラスボスのいない領域」で勝負するというものだ。
MNTSQ 代表取締役の板谷隆平氏は、弁護士から起業家への転身を通じて、この戦略の有効性を証明している。板谷氏の起業のきっかけは、大学の同期で AI エンジニアの安野貴博氏からの誘いだった。真面目に弁護士業務に従事していた板谷氏が、なぜ AI の世界に飛び込んだのか。その背景には、法務業界の構造的な問題への強い危機感があった。
板谷氏によると、弁護士として働く中で、本質的とは言えない業務が多くあったという。顧客に有利な条項を複雑な文言で盛り込んだり、リスク回避のための条項を大量に作成したりといった、形式的な作業が業務の中心を占めていた。
こうした問題意識が、AI 時代における法務業界の変革への取り組みにつながった。板谷氏は契約というものについて疑問を持ち、この業界は変わっていかなければならないと考えるようになった。
さらに、法務業界は最も AI によるリプレースメントが起こりやすい分野の一つでもある。
弁護士になってみたものの、やっていることといえば契約のフォントを10.5にして明朝体にし、第六条の次は第七条になっていませんと指摘することです。これ、意味がありますか?(板谷氏)。
こうした機械的な作業が業務の中核を占める現状に対し、板谷氏は強い疑問を抱いていた。
しかも、法務業界では知識の体系化が進んでいない。ナレッジが全然体系化されていない理由は、本質的に非構造化データが主役だからだ。主にファイルデータで構成される法務情報を効率的に扱うためには、大規模言語モデルの活用が不可欠だと考えたのだ。
差別化戦略

MNTSQ の事業戦略で最も興味深いのは、「契約というラスボスのいない領域」に着目した点だ。
契約データに特化したラスボスは思いつきません。SAPやSalesforce も、彼らが契約データに特化したすごい機能を出すかというと、また全然出していません。だから我々にとって、ある意味、エンタープライズ市場にもかかわらず、ラスボスがいないラッキーな分野です(板谷氏)。
この戦略の背景には、プロダクトの構造的な強さに対する深い理解がある。板谷氏は、プロダクトをデータベース、アプリケーション、UI/UX の3つのレイヤーに分けて考える。これまでは UI/UX が良く AI だと言い張ればプロダクトが成立していたが、これからはより本質的に自分たちにしか持てないデータは何か、自分たちのプロダクト上でしかできない業務は何かという、プロダクトの構造的な強さに立ち戻らないと生きていけない時代だというのが板谷氏の考えだ。
MNTSQ は、まさにこの構造的な強さを契約データの領域で構築している。三菱 UFJ 銀行をはじめとする大手企業で導入検証が進む中で、MNTSQ しか持たない契約データを蓄積し、そこに業務アプリケーションを構築することで、契約に関する業務が MNTSQ 上で朝から晩まで完結するような環境を作り上げているのだ。
MNTSQ のもう一つの特徴は、専門家によるプロンプトエンジニアリングの活用だ。
すべての弁護士をプロンプトエンジニアにすべきだと考えています。その分野で日本一の弁護士がプロンプトを書き、そのプロンプトに従って契約が作成され、交渉されます。そして法令が変わった時のプロンプトのメンテナンスの責任も、我々は弁護士事務所と提携して請け負います。
どんな契約をアップロードしても、最高の弁護士が作成したプロンプトが維持されています。これはユーザーにとってのベネフィットでもありますが、弁護士にとっての生存戦略でもあります(板谷氏)。
具体的には、MNTSQ は日本の四大法律事務所のうち3つと提携している。競争し合うはずの寡占プレーヤーが手を組むのは異例のことだが、これは彼らが自分たちの業務や仕事が完全にディスラプトされるかもしれないという強い危機感を持っているからこそ起こることだ。
MNTSQ の戦略で注目すべきは、AI に参照される信頼性の高いデータの生成に力を入れている点だ。例えば、法令改正があった時に、四大法律事務所の最高の弁護士が法令解説を書く。これは生成 AI が参照すべき、より信頼度の高いデータとなる。
板谷氏によると、こうした質の高いデータを生み出し続け、こうしたデータを参照すべきだということを AI に伝えるのは、自分たちのプロダクトのクオリティを向上させることでもあり、これは弁護士の生存戦略でもあるという。
AI に参照されるような質の高い知見を生み出し続けることで、その情報は社会的に信用される。そして社会的に信用されているから AI に参照され、AI に参照され続けるからこれからも信用されるという好循環を作り出している。
我々はかなりエンタープライズフォーカスです。スタートアップの中では日本では非常に特殊だと思いますが、日経売上高トップ100の会社では、我々はすでに大きなマーケットシェアを獲得してきました(板谷氏)。

MNTSQ の事例は、「魔王のいない領域」を見つけて参入し、その領域で構造的な強さを築き上げることの重要性を示している。汎用的な AI 機能では対応できない専門性の高い業務において、業界の専門家と連携しながらデータとアプリケーションの両面で差別化を図る戦略が、AI 時代の競争優位性構築の一つの解となっているのだ。
LayerX と MNTSQ の実践事例から見えてくるのは、AI 時代の「残酷さ」を生き抜くための明確な戦略だ。技術の深い理解により汎用ツールとの差別化を図り、プロダクトの構造的な強さによってリプレースコストを高め、大企業の要件に対応しながら専門家との協業を通じて競争優位性を構築する——。
「魔王」時代において生き残るために必要なのは、これらの戦略を組み合わせた総合的なアプローチなのである。大企業の内製化が進む中でも、企業固有の業務領域や専門性の高い分野において、新たなビジネス機会を創出する道筋が見えてきた。